「法定研修」の効率化で時間と負担を削減!現場で使える成功事例
メルキタ介護
2025.06.16
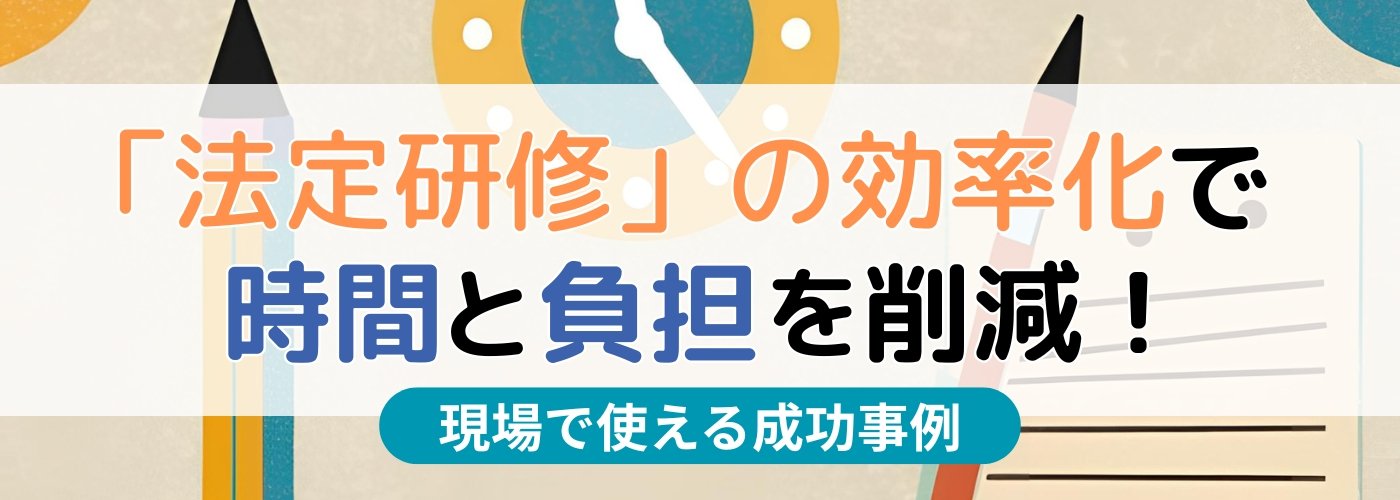 法定研修の増加で現場の負担が大きくなっている介護業界。特にBCPなど近年新たに追加された項目や新入職員への研修は、時間確保が難しい状況です。では、研修の質を保ちながら、時間短縮するためにはどうすれば良いのでしょう?現場で使える方法をご紹介します。
法定研修の増加で現場の負担が大きくなっている介護業界。特にBCPなど近年新たに追加された項目や新入職員への研修は、時間確保が難しい状況です。では、研修の質を保ちながら、時間短縮するためにはどうすれば良いのでしょう?現場で使える方法をご紹介します。
「義務」と「努力義務」を区別することから始める
研修は「義務」と「努力義務」に分かれていますが、多くの事業所では両者が混同され、すべての研修を全職員に実施しようとするあまり負担が増大しています。新入職員に本当に必要な法定研修は、施設系で5つ、在宅系で4つのみです。
・感染症防止研修
・業務継続計画研修
・高齢者虐待防止研修
・事故発生防止研修(施設系のみ)
これらを実施しないと介護報酬が「未実施減算」となるため注意が必要です。一方、認知症ケアやプライバシー保護などの「努力義務研修」は必要な職員だけが受ければ十分。この区別を行うだけでも大幅な負担軽減になります。
合同研修や動画の活用...効率化のためのさまざまな方法
研修資料をつくり、全員が集まる時間を確保し...とすると、どうしても大幅な負担は避けられないもの。しかし、効率化のためにはさまざまな方法があり、成功事例もあります。
○合同研修会や一括での実施
ある施設では研修内容を年2回に集約した上で複数事業所で共同開催し、準備負担を分散。外部から講師を招けば内容の準備も簡略化が可能です。また、「感染症予防」と「⾮常災害対策」などは「一体的実施」が認められているため、同時に実施する方法もあります。
○eラーニングや動画コンテンツの活用
基礎知識をオンラインや事前の自宅学習で習得。集合研修では実践部分のみ実施する方法です。教材には厚労省提供の動画など、繰り返し視聴できるものを活用します。ただし自宅学習を導入する場合は、その時間を労働時間に含めるなど、労務管理に注意が必要です
定期的な研修プランの見直しを
長期間事業を運営していると、前年度ベースに上乗せする形で研修が増えていきがちです。さらに職員のキャリアパスや加算取得のための個別の研修計画も必要になっています。すべての法定研修が全員に一律に実施すべき内容か、定期的に確認するよう心がけましょう。
多くの研修はサービス品質や安全面の向上が目的とされていますが、負担のあまり業務へ支障が出たり、新入職員の離職につながったりすると、本末転倒です。今回の方法で効率化と質の両立を図れるよう心がけましょう。
※この記事は2025年4月17日に開催したジョブキタオンライン勉強会「入職研修の効率UPセミナー」の内容を元に制作しています。

●ふくしのよろずや神内商店合同会社
代表 神内秀之介さん
公益社団法人日本社会福祉士会理事を筆頭に数多くの肩書を持ち、介護経営のコンサルタントとして、福祉業界のサービスや経営環境、就労環境の向上のために講演活動やさまざまな経営のアドバイスを行っている。

