よく聞くけど深くは知らない!?ATS(採用管理システム)の基本と導入メリット!
メルキタ
2024.07.16
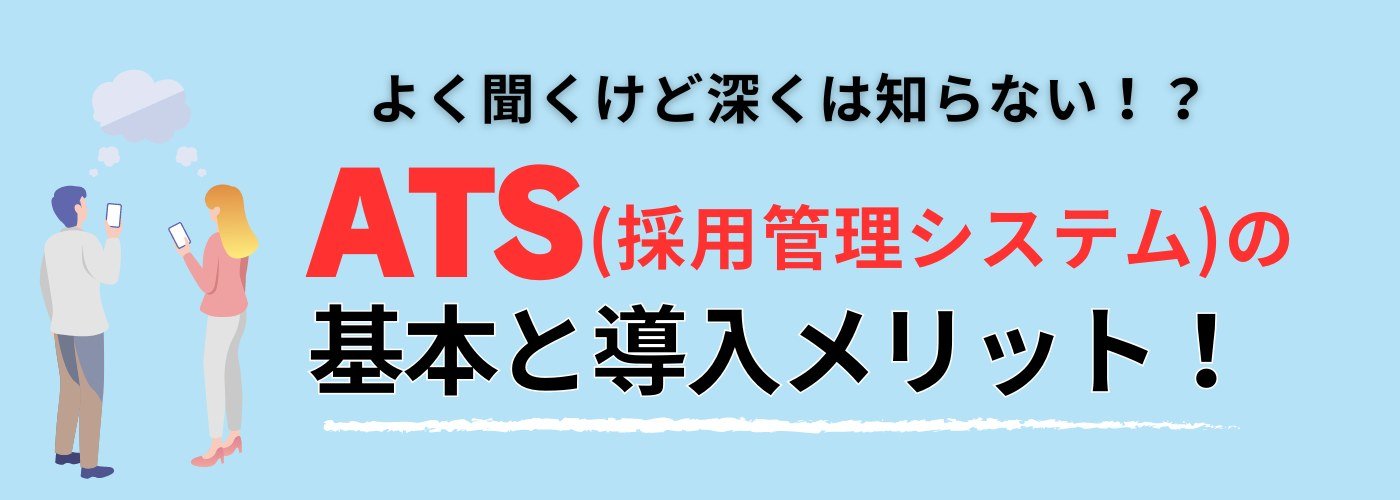 ここ最近、求人関連のキーワードとして耳にする機会が増えた「ATS(採用管理システム)」。とはいえ、実際に利用している採用担当者の数はまだまだ少ないはずです。今回は、ATSの基礎知識やメリット、採用課題に応じたサービスの選び方などを分かりやすくご紹介します。
ここ最近、求人関連のキーワードとして耳にする機会が増えた「ATS(採用管理システム)」。とはいえ、実際に利用している採用担当者の数はまだまだ少ないはずです。今回は、ATSの基礎知識やメリット、採用課題に応じたサービスの選び方などを分かりやすくご紹介します。
ATSとは?
ATSとは「Applicant(応募者)Tracking System(追跡システム)」の略で、一般に採用管理システムと呼ばれています。
従来の採用業務を大まかに分解すると、下記のようにさまざまな連絡ツールや各種調整が必要でした。
(2)応募受付の連絡(電話・メール・求人メディアの管理画面など)
(3)履歴書の受け取り
(4)書類選考(場合によっては現場の上長などと検討)
(5)面接の予定調整(社内・応募者)
(6)面接
(7)応募者への採用・不採用の連絡(電話・メール・求人メディアの管理画面など)
(8)採用
ATSは、こうした一連の業務を一元的に管理できるサービスです。サービスによってそれぞれ機能が異なるので一概にはいえませんが、求人情報の公開から応募者情報の管理、選考プロセスの進捗確認(面接済/書類受取済など)、応募者とのやり取りまでを完結できるため、採用担当者の負担をグッと軽減できるのが魅力の一つです。
ATS導入のメリットは?
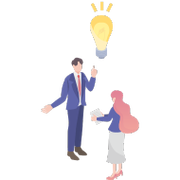
採用担当者の負担軽減以外にもATSを導入するメリットはあります。
拠点数が多い企業や一つの施設で複数職種が働くケースにおいては、求人広告を出稿する際に費用がかさむことも少なくありません。ATSは初期費用がかかるものの、月額定額制で自社採用サイトを持つことができ、Indeedなどの求人サイトや検索エンジンとも連携して多数の求人情報を掲載できるものが一般的なので、広告費用を最適化し、コストカットにつながることがあるのもメリットです。また、サブスクリプションのため、契約中は期間の制限なく、求人情報を「発信し続けられる」のもプラスに働きます。売り手市場の今、求職者が仕事を探すタイミングはいつ生じるか予測ができません。情報を常に公開することにより、募集のターゲットになり得る人がいつ求職活動をスタートしても良い状況をつくることができるため応募につながりやすいと言えるでしょう。
ATSの選び方
ひと口にATSといっても、サービスによって機能や特徴、採用サイトの設計や、提携している求人メディア・Indeedへの課金形態にも違いがあります。例えば、選考プロセスに強いATS(応募書類・面接の進捗管理や、面接スケジュール調整・リマインダー、WEB面接機能など)や、応募者の管理に強いATS(応募があった候補者とのやりとりを一元管理、自動返信、履歴の分析など)、データ分析に強いATS(採用プロセスにおけるデータを収集・レポート化、募集時期や条件の効果測定など)、中小企業に強いATS(応募者との連絡管理など基本の機能を直感的に操作でき、定額料金がお手頃・初期コストが低い)などがあります。ATS導入の際は、このようにさまざまな特徴を持った多数のサービスから選り抜く必要があります。どんなサービスを選べばよいか分からないという場合には、採用活動に生じている支障を洗い出し「ATSにやらせたいこと」から選ぶのがオススメです。
「面接スケジュールを組むのが大変」→選考プロセスに強いATS
「すべてを使いこなすのは難しそうなのでシンプルで良い」→中小企業向けATSなど
最後に、メリットも多いATSですが、残念ながら導入=採用成功ではありません。
自社の求人情報を常に公開できることは成功への一歩となりますが、仕事内容や職場の雰囲気などを、求職者の目線でわかりやすく伝える必要性は従来通り変わっていません。また、終了した募集を非公開にするなどの最新情報への更新や、掲載職種の変更といった適切な運用をすることも大切です。その点を踏まえ、ATS導入にはサービスのみならずパートナー選びも大切なポイントと言えそうです。

