新人でも慌てない!「やさしい入職時BCP研修」とは?
メルキタ介護
2025.08.18
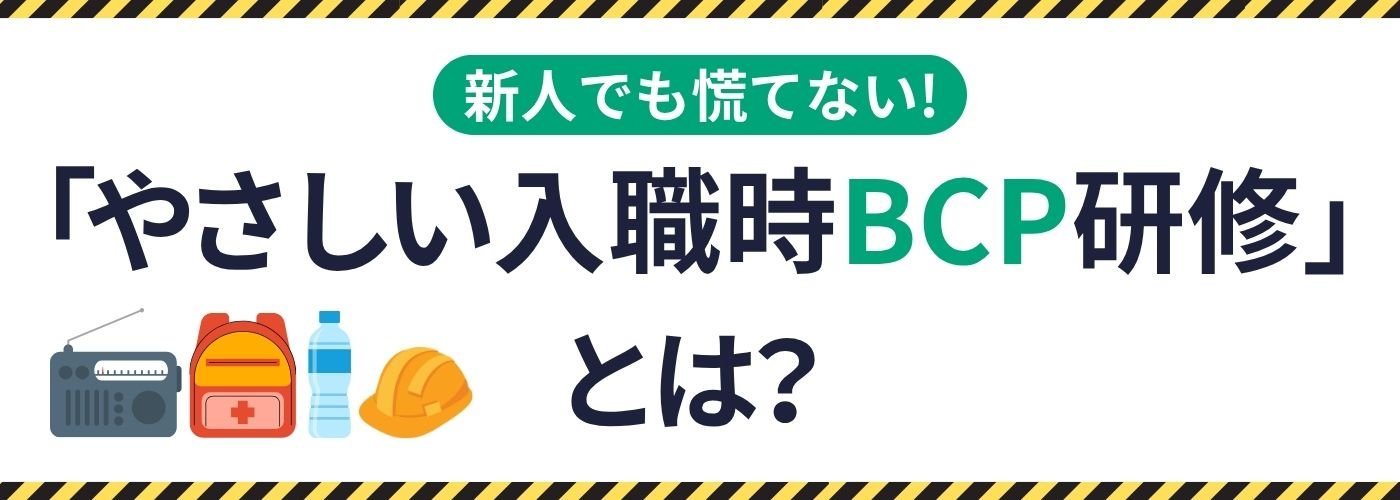 2024年4月に義務化された事業継続計画(BPC)の策定。自然災害や感染症が起きた際に従業員を守り、事業の復旧と継続を実現するために何をすべきかをまとめているもので、研修や訓練の実施が運営基準上で定められています。しかし「新人さんに難しすぎて理解してもらえない」「全部説明しようとすると時間がかかりすぎる」と悩みを抱えている事業所も少なくないはず。今回は新入職員向けBCP研修を効果的に行うコツについてご紹介します。
2024年4月に義務化された事業継続計画(BPC)の策定。自然災害や感染症が起きた際に従業員を守り、事業の復旧と継続を実現するために何をすべきかをまとめているもので、研修や訓練の実施が運営基準上で定められています。しかし「新人さんに難しすぎて理解してもらえない」「全部説明しようとすると時間がかかりすぎる」と悩みを抱えている事業所も少なくないはず。今回は新入職員向けBCP研修を効果的に行うコツについてご紹介します。
新人が覚えるべきは、まず「3つの心得」だけ
新入職員にBCP計画書を渡して「読んでおいて」とするだけでは効果は期待できません。まず覚えてもらうべきは、緊急時の基本行動となる「3つの心得」です。
1.慌てず、まず報告すること。
利用者や同僚に発熱、怪我、被災などがあった場合はすぐに上司や管理者に連絡するよう伝えましょう。
2.自分で判断せず、指示を仰ぐこと。
行動によっては被害を拡げかねないため。「誰の指示を聞くか」も合わせて教えるようにしましょう。
3.マニュアルとBCP計画書を確認すること。
それぞれの役割分担や連絡網についても記されています。マニュアルがどこにあるかも明確に伝えましょう。
「誰」に「何」をする?大切なポイントだけを伝えよう
BCP計画書は膨大な内容を含んでいます。一度に全てを把握することは難しいため、新入職員にはまず重要なポイントを絞って教えることが効果的です。
1.役割分担表・・・緊急時の自分の役割と、代行者の確認
2.連絡網・・・「誰が」「誰に」連絡するかの流れ
3.備蓄品リスト・・・災害・感染対応物品(マスクや備蓄食料等)の保管場所
「まずはここだけ」と範囲を限定することで、新人の負担を軽減しながら実践的な知識を身につけてもらえるでしょう。
シミュレーションや体験で理解度アップ
机上の説明だけでなく、実際に体験することで新人職員の理解度は格段に向上します。短時間でも効果的な訓練を取り入れましょう。また「災害」と「感染症」でも対応が異なることを伝えておきましょう。
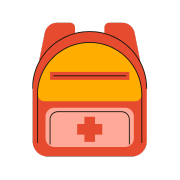
・地震発生シナリオのシミュレーション:「午後2時、施設内で震度5強の地震が発生。停電し、固定電話・Wi-Fiも不通。利用者10名が滞在中」という想定で、新人職員が安否確認と避難誘導の手順を体験
・ハザードマップの確認:事業所周辺のリスクを地図で確認し、避難経路を複数ルート検討。職員の自宅からの通勤可否も話し合う
・非常用物品の実体験:非常食を実際に食べてみる、簡易トイレを組み立ててみる、懐中電灯の電池確認など、「使えるかどうか」を体験
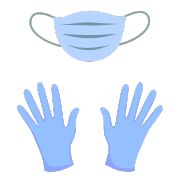
・感染症発生シナリオのシミュレーション:「午前9時、来所した利用者が37.8℃の発熱。咳もあり体調不良」という想定で、新人職員が発見から報告、隔離、家族連絡までの一連の流れを体験
・PPE着脱の演習:ガウン、マスク、手袋の正しい着脱をペアで実践。
・ゾーニング体験:汚染区域と清潔区域を実際にテープで区切り、動線を意識した移動を体験
・嘔吐物の処理実演:寒天に絵の具を混ぜた教材をわざと飛び散らせ、どの程度拡散するかを実体験。その後、新聞紙とPPEを使った正しい処理手順を実演
上記のような訓練が難しい場合、机上訓練でも十分効果があります。いずれも重要なのは「自分だったらどうするか」を具体的に想像させること。グループディスカッション形式にして他職員の意見を聞くことでも、新たな視点や気づきが得られるでしょう。
詰め込むより「習慣化」で備えよう
新入職員に一度に研修を詰め込むと「ついていけない」という不安の原因にもつながってしまいます。はじめから完璧を求めず、「明日から困らない最低限の知識」から始めて、定期的な見直しと訓練を通じて徐々にレベルアップを図りましょう。少しの工夫で、新人職員も安心して働ける環境づくりが可能になるかもしれません。
※この記事は2025年6月19日に開催したジョブキタオンライン勉強会「これで大丈夫!やさしい入職時BCP研修のコツ」の内容を元に制作しています。

●ふくしのよろずや神内商店合同会社
代表 神内秀之介さん
公益社団法人日本社会福祉士会理事を筆頭に数多くの肩書を持ち、介護経営のコンサルタントとして、福祉業界のサービスや経営環境、就労環境の向上のために講演活動やさまざまな経営のアドバイスを行っている。

